COMMITMENT TO RICE FARMING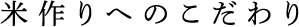
美味しいお酒を造るために、原料のお米にこだわるのは当然のことですが、酒造りに寄り添う栽培設計をすることが重要です。水や土、地域の自然と向き合い、自分の蔵の酒造りの現場にあった酒米を栽培して最高品質の日本酒を目指すのが当蔵の理念です。

6代目当主が、当時23歳(1986年)で蔵に戻ったとき、決算書をみるとお酒の原価のうち半分以上がお米代でした。当時はすべての米穀流通や価格が国管理のもと、大きい酒造メーカーも小さい酒造メーカーも購入条件が一緒でした。しかし、それに安んじている事に未来への不安を感じました。そして、取り組み始めたのが自社栽培でした。
米作りを始めて最初の25年ぐらいは「自己満足だろ。」とか「原価が安くなるから?」というお言葉が大半でした。周囲の目は極めて冷ややかで孤独の一言につきます。
最初は3反5畝の圃場(ほじょう)からスタートしましたが、現在は20町近く、枚数は60枚を越えています。ここまでくると、圃場に入り土の感触を確かめ「この辺は麹米に、そこの圃場は掛け米向きだ」などと思い浮かび、お米作りとお酒造りの関係性が見えてきます。もちろん現在では、すべての圃場の土壌分析を行い、データによって正確な土壌管理と目的ごとの施肥設計を行います。
外見だけを基準にする穀物検査に頼り切らずに、お酒造りに寄り添うお米作りを行うのが最も正しい酒米栽培であると確信しています。

酒造りをしない米農家さんが作る酒米より、酒造りに特化した蔵人目線の納得のいく酒米が欲しかったからです。農家さんはお米を栽培する時、より良い米=等級の高い米を作るために大粒の米を作ろうとします。大粒の米を作るためには肥料を増やします。しかし、肥料の主成分は窒素。窒素は米のタンパク質成分を増やしてしまいます。しかし、タンパク質は酒のオフフレーバーを生み出す原因なのです。一方で酒蔵は、米のタンパク質を減らしたいがために高精米を行う。私たちはこの流れを「タンパク矛盾」と呼んでいます。
実は最初のうちは自分たちもよくわからず、ひたすら等級の高いお米作りを狙っていました。真実を教えていただいたのが永谷正治先生でした。その教えは「三黄(さんおう)の稲作り」です。
三黄作りとは、稲を3回飢餓状態にさせ、稲本来の潜在能力を引き出し倒伏などを防ぐ農法です。
1回目の黄は、苗の生育で田植え前の時に、やや緑色が落ちた状態にする。目的は苗が栄養不良になることによって、田植え直後の活着を良くする。事実、田植えしたあと苗が緑色に変わってくる。
2回目の黄は、8月頭に幼穂形成期(ようすいけいせいき)に窒素分を下げ、緑色がやや退色する。この時稲の成長から穂の育成へ養分を切り替える必要があるが、窒素過多だと体内の切り替えが遅れると言われる。
3回目の黄は、稲刈りのときの稲の色で、この時緑色が強すぎるということは、稲の体液の窒素分が多いことを意味し、それは米にタンパクが蓄積されることを意味するので、強い緑色は好ましくない。
なお、稲の倒伏を避ける一つの有効な方法として、ポッド苗方法がある。ばら撒きの苗箱と違い、田植え時に苗の根を破壊せずに田植えをすることができる。その結果、一般ばら撒きは縦に稲が成長するのに対し、ポッド苗は田植え後、稲も太く広がる様に成長する。田植えの時点で、その後の稲の姿が決定づけられている側面がある。
昭和10年広島生まれ。昭和32年から平成3年まで国税庁で酒造工学の研究・開発に従事され、その後各国税局の鑑定官室長を歴任され退官後は、酒米栽培指導にも取り組んでこられました。著書には「山田錦の作り方と買い方」、「花酒」醸界タイムス社などがございます。 現在、山田錦が兵庫県にとどまらず、各県で栽培されているのはなぜでしょう。すでに徳島の阿波JAでは品質区分による収穫が実現されています。永谷先生なくしてありえません。その永谷先生は平成9年5月5日に他界されました。

お酒造りに寄り添う米作りの、もう一つのひとつの方法として、麹米用と掛米用の「目的別の栽培」。圃場は一枚一枚個性があり、まずその適性を調べ、それぞれの目的に合わせた圃場の選択と施肥設計を行います。そのためには全ての圃場を土壌分析し、3年ほどかけて土壌改良を行い、そうして作り分けたお米を目的別に分けて収穫し、乾燥、籾摺り、調整、保管までを目的別に区別する「選択収穫」を行っています。










